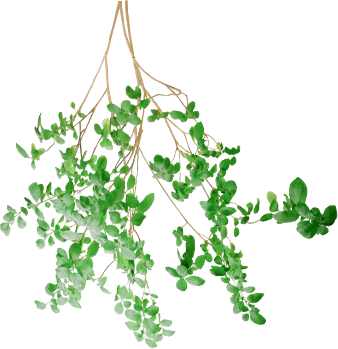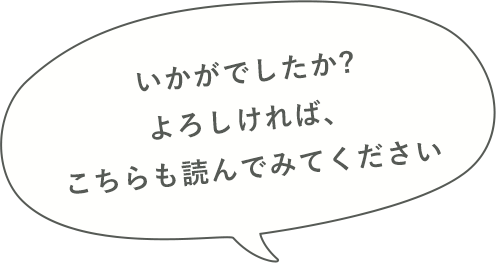なぜできたのだろう??
こんにちは、学びの森の樋口です。
最近、個別学習の場面でとてもおもしろいな、考えたいなと思うことがあったので書いてみようと思います。
きっかけは、ある子が国語の学習中、対義語の問題について質問に来てくれたことでした。
選択肢の中に「合図(あいず)」という言葉があり、「これって何?」と聞いてきました。
聞かれたとき、私はすぐにうまく説明することができませんでした。
今振り返れば、「なんとなくこういう意味だよね」という程度にしか、「合図」という言葉を理解できていなかったのだろうと思います。
そこから国語辞典や漢字辞典を使って調べていくと、さらにその子は「『合』はなぜこの漢字を書くの?」「訓読みでは『う』が送り仮名なのに、なぜ『試合』という言葉になったら一文字で『あい』と読むの?」など、深い問いを次々と投げかけてくれました。
もちろん、私は明確に答えることはできませんでした。
そのときできたのは、その子といっしょに「たしかに、なぜなんだろう?」と考えることだけでした。
やり取りを進めるうちに、「逆に、私はどうやって漢字や言葉の意味を覚えてきたのだろう?」という問いにぶつかりました。
「前提が崩れる感覚」とでもいうのでしょうか。
私自身は、比較的読み書きが好きな人間で、学習に大きくつまずくことなく義務教育を卒業できました。
一般的な学習方法で、すなわち授業を受け、問題を解くことを繰り返して、言葉の意味などについて立ち止まって考えることもほとんどなく、学習を進めてきました。
しかし、目の前にいるその子は、「言葉の意味がわからない」というところで立ち止まってしまい、そこから先へ進めずにいました。
また、「わからない」ことを掘り下げて、問いを立て、言葉の本質的な部分から理解しようとしていました。
一般的には、「偏差値が高い」「勉強ができる」というと、「教科書などに書かれてある一つひとつの言葉、文脈を大まかにつかみ、全体の内容を捉えることができる」というイメージがあります。
一方で、1つひとつの言葉を本質から理解しようとするタイプの子どもたちにとっては、全体の内容を理解するまでの道のりは、かなり遠く感じられるのでしょう。
では、「1つひとつの言葉、文脈を大まかにつかみ、内容を捉える」ことができることだけが全てなのでしょうか。
ちなみに、比較的「偏差値が高い」「勉強ができる」側だった私は、冒頭の通り、ありふれた言葉の正確な意味1つにすら苦戦しています。
「1つひとつの言葉を本質から理解する」ことにはたしかに時間がかかりますし、効率的ではありませんが、本質に深くつっこんで考える経験や、そこから得た学びにも、何か重要な価値があるのではないか、と私自身は感じています。
少なくとも、一般的な学習方法になじまない子たちを「勉強が不得意」とラベリングしたり、一般的な学習方法を強制するのは、「勉強ができる」ことの弱い部分や、勉強の本質、学びの本質などを考え、よりよい学びを追究するうえではもったいないのではないかと思います。
とはいえ、現実としては、効率性や進捗を全く考慮しないわけにもいきません。
進むことと立ち止まることのバランスは、また改めて考えることにしようと思います。
…と、立ち止まって考え、ブログを書くうちに時間がかなり経ってしまいました、、、
せっかくなら、面白いなと思うことを、楽しく、真剣に、みんなで考えたいものですね。