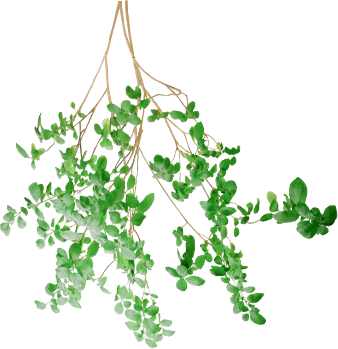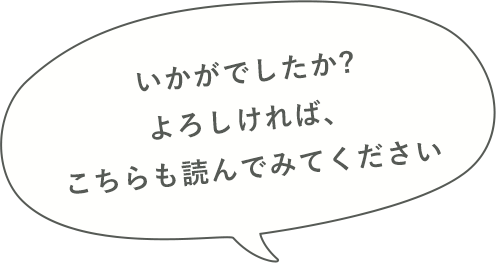ともに外へ向かう媒介者として~フリースクールにおける「教師」とは?~
学びの森の概要
「学びの森」は京都府亀岡市にある学校外の学びの場である。もとは「学習者が中心の学びの場をつくりたい」という思いから始まった私塾だった。そのため教室は学校とは違って、真ん中に大きなヘゴシダの木があり、色々な形をした机が配置され、クラッシックの音楽が流れる有機的な空間となっている。ここに一人の不登校生がやってきたことによって、現在事業の核となっている「フリースクール」と「ハイスクール」が生まれた。
フリースクールは小中学生を対象としており、京都府教育委員会の認定も受けている。学びの森への出席が在籍校への出席になることや、定期試験を学びの森で受けることなどが認められている。ハイスクールは、高校生・高認予備校生を対象としており、高卒資格の取得や高認受験だけでなく、その後の大学や専門学校の受験もサポートしている。
学びの森は、学校教育からふり落とされた児童・生徒の単なる「居場所」ではない。一人ひとりが自分のペースで学びながら、少しずつ自信を取り戻し、自分の過去や現在と向き合って、たくましく次の進路を切り拓くための「変容の場」である。現在、学びの森には約20名の児童・生徒が通っている。彼、彼女たちが変容し、学びの森から次なる「社会」に出ていくために必要なことは何か?こうした問いに応えるために、学びの森は教育の在り方や学びの在り方を絶えず模索し続けている(詳しくはhttps://manabinomori.co.jp/を参照)。
私はこの学びの森で働き始めて4年目になる。今回の記事では、私が学びの森に関わってきた3年間を振り返りながら、現在抱えている問いについて書きたいと思う。
自己変容と物語の書き換え
1年目の出来事として大きかったのは、自分の中で「学び」の認識の幅が拡がったことだった。私はそれまで、教師が板書したことや教科書に載っていることをノートに写し、テストの前にそれを暗記すること、それによって知識を蓄積していくことが「学び」だと思っていた。またそう思う前提には、教師が何かひとつの正解を持っていて、生徒はそれを教えてもらう無知な存在であるという枠組みがあった。しかし、授業の中で生徒たちと対話を進めるうちに、こうした「学び」の認識やその前提となる枠組みがどんどん変化していった。知識を蓄積していくこともひとつの「学び」ではあるが、それぞれが自分の頭で考えて、他者と対話し、自分なりの答えをつくっていく過程やその繰り返しも「学び」ではないかと考えるようになった。そしてその前提となる枠組みとは、教師も生徒もともに「学習者」だということだった。
私の中でこうした自己変容が起こることは、それまで自分を支えていた「学校的価値観」が変わることも意味していた。私にとって、教師が持つ正解を暗記し、テストでそれを発揮できさえすればおのずと評価される「学校的価値観」から、その価値観を越える新しい価値観をつくりだすのはとても困難な作業だった。また、新しい価値観から私のこれまでの人生を振り返ったときに作られる物語は、学校に通い続けた自分を否定的に捉える物語でしかなかった。しかし、生徒たちとの関わりの中で、徐々にその物語は書き換えられていった。学校に通い続けたことが「問題」ではないし、学校に通い続けていたからこそできることが自分にはある。それをどうしたら発揮することができるのかを生徒との関わりの中で学んだことにより、私の物語は学校に通い続けた自分を肯定的に捉える(むしろそういったことに囚われない)物語となった。
経験を外に、自分の内に閉じない
2年目の後半から、私は色々なところにフィールドワークに出かけるようになった。学びの森の中だけでなく、外に出て学びたいという気持ちが強まっていたのだ。大阪の「釜ヶ崎」という地域で行われている運動や、そこを拠点に活動しているNPO法人を紹介してもらって話を聞きに行ったり、そこの企画に参加したりするようになった。また、東九条にも足を運び、歴史的背景を教えてもらったり、資料館をまわったりした。東九条にあるブックカフェでバイトをしながら、自分が今どんな活動をしているのか、どんなことを知りたいと思っているのかなどを積極的に話すようになった。そんな風に行動している中で、私は色々な人に助けてもらいながら、自分の知らない世界が現実にたくさんあることを知った。また、そうやって学びの森の外に出る経験を通して、人と人とのつながりの中で学ぶ「怖さ」と「楽しさ」、その経験を積むために必要な「姿勢」も知った。
私が「怖さ」と言ったのは、相手のことを知らない状態で自分をさらすこと、自分は何者で何が目的でこういう活動をしているのかを常に問われること、自分の無知さゆえに拒絶される可能性があること、何が起こるかがわからないことなどである。また、「怖さ」と表裏一体となって「楽しさ」があると思う。つまり、自分をさらしたり(自分を外に開いたり)、常に自分自身を問われたりしながら、他者と対話し続けることで、自分が更新されていく感覚や、そうすることで新しいものが生まれる(一緒につくっていくことができる)感覚が「楽しさ」である。また、こうした感覚を持つために必要な「姿勢」があると私は考える。その「姿勢」とは、「怖さ」を引き受けながら、自分のことを常に問い続けることであり、そのために他者や現実を知ろうと対話を続けることだ。こうしたことは、学びの森という環境だけに身を置いていたら気が付かなかったことだ。学びの森という環境やそこで築かれる人間関係は、決して広いとは言えない。自分とは全く違う経験をしてきた他者と初めて出会ったときの緊張感や、そういった他者とのつながりをどうやってつくっていくのかを常に意識して行動すること、つながりができて自分の世界が広がっていく喜びなどを経験するには、文字通り外に出ていくしかないと思う。私はフィールドワークを続けていて、「学ぶ」とは自分の中に閉じることではなく、自分が持っている経験を他者に開き、お互いに経験を突き合わせてその違いや同じ部分にふれ、お互いの経験を再構築していくことの繰り返しだと考えるようになった。また、そんな風に「学ぶ」ことができるような場を、学びの森の内外につくっていきたいと考えるようになった。
私はこの経験が、学びの森の生徒たちにも必要だと考えた。なぜなら、今後進学や就職などなんらかの形で社会に出ていく生徒たちにとって、学びの森で培われる「人とつながる」経験だけでは狭すぎると考えたからだ。私は学びの森で学んだことを、自分だけのものとしてとどめていても意味がないと思う。もっと外に、他者に開いていくことで、自分が学んだことはさらに深まるはずであり、そういう学びの循環を自ら創り出していく力が、社会に出た後も必要になる。私自身の経験からそんなことを考え、フィールドワークは私が担当するゼミの活動のひとつとして位置付けた。私はフィールドワークを、事前に学習した中で出てきた問いについて、街を歩きながら、街を案内してくれる方も一緒に考えるようなものにしたかった。そういった意図を協力してくださる方に話しながら、一緒に学びの場をつくる過程は、まさしく自分の経験と他者の経験をつきあわせ再構築していく過程だった。フィールドワークでは、普段できないことをたくさん経験させてもらった。生徒たちと振り返りの時間を持ち、そこで出た意見や疑問をフィールドワークに関わってくれた人たちに報告し、それについての感想をいただいた。そんな風に自分たちが経験したことを外に開くことで、新しい経験の機会がうまれていくことの総体が「学び」になっていた。フィールドワークを続ける中で、反省もあった。それは、生徒たちを「閉じた」存在であると見ていたことだ。つまり、学びの森という狭い世界から出て他者に「開く」経験が生徒たちには足りないと思っていたのだ。しかし、フィールドワークに参加する生徒たちの姿を見て、これは大きな間違いだと思った。生徒たちは、私がどうこうする以前に他者に「開いていた」のだ。初対面の人にも堂々と話しかけたり、話しかけられたときにもしっかりと対応していた。今後は反省を踏まえて、自分がフィールドワークをすべて用意するのではなく、生徒がフィールドワークを企画・運営していけるように手伝おうと思っている。
フリースクールにおける「出口」
今年に入って、私の中で「出口づくり」というキーワードが出てきた。それは、学びの森ハイスクールに通う生徒たちが、ここを卒業していくときの「出口」をどうやって作っていくか考えるというものだった。ハイスクールの生徒たちの中には、中学校から学校教育を体系的に受けていない生徒もいる。そういった生徒たちにとっては、現役で大学入試に挑戦するという選択肢はハードルが高い。入試科目が少ない私立大学を目指すならまだしも、国公立大学を目指すとなると、どうしても限界があると私は思う。しかし、それはいわゆる一般入試という方法で受験をした場合だ。AO入試や小論文入試なら、学びの森にやってきたからこそ得られた経験をもとに、大学進学という「出口」を目指すことができるかもしれない。あるいは、大学進学だけではない別の「出口」、つまり学びの森の内外で築いてきた人とのつながりの中で「出口」を見つけ出すことも可能なのではないか。そういった「出口」をつくっていくためには、フリースクールという場所が社会の中でもっと認知される必要があると思う。冒頭に書いたように、学びの森は学校教育からふり落とされた児童・生徒の単なる「居場所」ではない。しかし、世間の認識は単なる「居場所」であったり、「何をしているかよくわからないところ」であるというのが大半だと思う。学びの森の生徒たちの「出口」となる選択肢を増やすためにも、フリースクールが多くの人に認知されるためにも、外に開いていくことが必要だ。
そういったことを踏まえて、今年のフィールドワークをどうしようか考えていると、一人の生徒が立命館大学を志望していることがわかった。そこで、私は立命館大学の学生たちと交流の場を設けることにした。目的は、教職課程を履修している大学生たちに、不登校の実状を知ってもらうことと、学びの森の生徒たちに具体的な大学のイメージを掴んでもらうことだった。学びの森の生徒たちからは、「不登校の生徒」ではなく「一個人」として交流がしたいという意見が出た。私はこの意見を踏まえて、お決まりの「不登校」像や「大学」像を持ち帰るのではなく、それぞれの経験を突き合わせながら、その個人を通して「不登校」や「大学」のことを考えることができるような内容を考えた。
参加者はみんな、予定していた時間では話し足りないという感想も出てきたぐらい活発に意見を交換していた。学びの森の生徒たちにとって、同年代の人たちとの関わりは新鮮だったのだろう。振り返りではもっと同年代の人たちとの関わることができる場を持ちたいという意見も出た。こうした思いが、後述するフォーラムの企画・運営につながっている。私自身も彼、彼女たちを見て、自分と同世代の人たちと何かしたいと思うようになった。私がこれまでの活動で得た「学びの場をともに創る」経験を、もっと色んな仕事をしている同世代の人たちと関わりの中で活かしていきたいと思うようになった。
フリースクールにおける「教師」とは?
こうして振り返ってみると、私は「自分に今何が必要か、次どんなことをしたいか」を考えながら行動する一方で、「今学びの森の生徒たちに何が必要か」を考えながら行動していたことがわかった。私は今まで自分がしていることを「教育」と考えてはいなかったし、自分の立ち位置も「教師」ではないと考えていた。しかし今は、自身の活動を通して得た経験を生徒へ還元しようとする行為は「教育」であり、それをおこなっている自分はまぎれもない「教師」だと考えている。特に、自分の経験を外に開き社会とつながる活動は、フリースクールが生徒たちにとって単なる「居場所」ではなく「変容の場」であるために、そして生徒たちの「出口」をつくりだすために必要なものだ。したがって私は、生徒たちが外へと向かうときに「媒介者」となりうる存在が、フリースクールの「教師」のひとつの形であると考える。