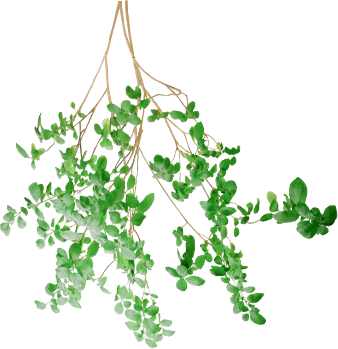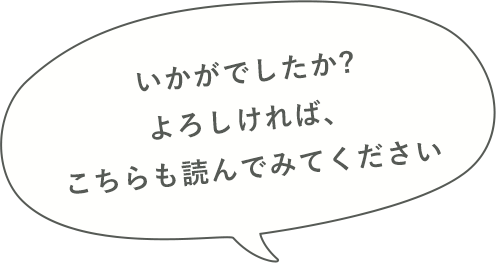「学び」のおもしろさ
こんにちは、学びの森の樋口です。
9月1日、22日に行われた教養講座(小学生)の様子をお伝えします!
さて今回のテーマは、「お金」です。
講師として、プラスソーシャルインベストメント株式会社社長の野池雅人さんにお越しいただき、お金の役割や歴史、会社の仕組みなどについて教えていただきました。
各回ともに印象的だったのが、ゲームを通した小学生たちのやり取りや発想です。
1日は、2人ペアで、手持ちのカードに描かれたものを交換する、物々交換のゲームをしました。
「同じ野菜だから、ニンジンとブロッコリーは交換できる」など、現実において価値の近いものを考える人もいれば、
相手からほしいと言われたけど、手元に残しておきたい…と悩む人もいました。
また、「何でも好きに交換する」という条件と、「無人島で生き残るために必要なものを考えて、交換する」という条件では、
交換したいと思うものも、その理由も大きく変わりました。
物々交換では価値を測れないから、「お金」という共通の価値をはかる基準が必要であるということや、
手元に持っておきたいと思うもの、ほしいと思うもの、またその理由をしっかりと考えることが、お金を使ううえでもとても大切であることを、
難しい言葉や複雑な説明でつまずくことなく、感覚的に、理解してくれていたのではないかと思います。

また22日は、グループで商品を1つ考え、投資家役のスタッフたちにプレゼンするというゲームをしました。
それぞれのアイデアに加え、「どういうところが役に立つか?」「どんな人のためにつくるか?」など、商品を考えるうえで必要な視点もふまえながら、話し合って、アイデアをまとめて紙に書き、形にしてくれていました。
そして出てきたのは、「ある場所を指すだけで、瞬間移動して旅行できる地球儀」「入力した言葉が、ふせんにメモされて出てくる機械」「描いたものが実物になって出てくるタブレット」などなど…
少々現実から離れてはいるものの、実現したら本当にすごいものになるだろうな、と思うようなものばかりでした。
小学生たちの発想になぜか心が洗われた(?)私は、投資家役ながら、全て購入してしまいました。

さらに、ゲームだけでなく、お金の歴史やお金の役割について学ぶ時間もありました。
ここに、教科学習における学びと、教養講座における学びの違いが、明確に表れていたように思います。
教科学習においては、たとえば「奈良時代の貨幣は和同開珎」など、歴史上のある時代や、ある国におけるお金の在り方を、
断片的な知識として学ぶことが多いように思います。
一方で、今回の教養講座では、「お金」というテーマにしぼり、「歴史上でお金の在り方はどのように変わってきたか」という視点から、時代・国などにとらわれず、横断的に学びました。
また、実際にお札を観察したり、お金のいいところ・悪いところをそれぞれで考えたりしたことも、単なる知識が、少し身近に感じられることにつながっていたかもしれません。
比べることは一概には難しいですが、もしかしたら、教科書や問題を使う、一般的な学び方で得た「学び」よりも、ゲームなどの楽しい経験といっしょに、より印象や記憶に残る「学び」になったかもしれないな、と思います。
根拠はとくにありませんが、強いて言えば、小学生たちのとてもわくわくした、明るい表情といったところでしょうか。
「おもしろい!」「そうなんだ!なるほど!」など、新鮮な発見を、驚きや楽しさをもって味わう瞬間の感覚は、大人になっても忘れたくないなぁ…と思うこの頃でした。