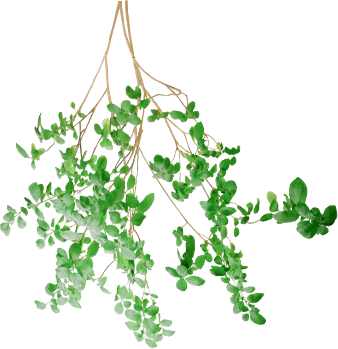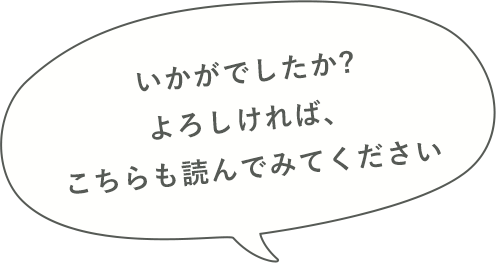2学期第2部、始動!
こんにちは、学びの森の樋口です。
学びの森の2学期がスタートして、昨日でちょうど1カ月が経ちました…!あっという間ですね。
そしてそして、ようやく昨日、2学期の時間割を生徒一人ひとりが決めることができました。
今日からは、各自が決めた新たな時間割に沿って、学習を進めています。
学びの森には、「自分の時間割は自分で決める」というならいがあります。
1日5コマ×4日分(水曜も通う人は+2コマ)、合わせて20(22)コマ設定されており、生徒一人ひとりが、自分に合った時間割を考えてつくっています。
(運動や、ゼミ・教科演習など集団で同じことに取り組む時間は、あらかじめ設定されています。)
例えば「苦手科目は午後にしたい」「好きな教科しかしない日をつくりたい」など、それぞれにこだわりがあるようで、個性が垣間見えたりもします。
ところで、2学期の時間割を生徒たちが決めるまで、なぜ開始から1カ月もかかってしまったのか?
そこには、1学期の反省として出てきた「ゼミは何をする時間なのか?」という大きな問いがありました。
これまでは、おおむね集団で学習する時間のことを「ゼミ」とくくって呼んでいましたが、その内容は先生によってさまざまでした。
教科の学習を集団で行う、学校の授業に近いものもあれば、あるテーマをめぐって自由に表現したり、議論して考えを深めたりするものもありました。
私(樋口)は今年度から入職し、4月当初から「ゼミ」を担当することになりましたが、
こんな感じの「なんでもゼミと呼ぼうと思えば呼べる」状況に混乱し、「ゼミって何なんだ?」という大きな問いにぶつかりました。
他にも、「ゼミが多すぎる」という声が4月に生徒から上がっていたり、一部スタッフ間で、「ゼミ」の歴史を振り返ったり…
などなど、「ゼミ乱立状態」をなんとかしよう!という動きが、静かに広がっていました。
そうして、時間をかけてスタッフ間で様々な議論を重ねた結果、2学期からは、これまで全て「ゼミ」と呼んでいたものを、
「ゼミ」と「教科別演習」に分類することとなり、それぞれの定義(暫定)がつくられました。
全員で共有したプリントから、その定義を引用しようと思います。
「ゼミ」…教科のことを通して/教科を横断して/教科の枠組みを超えて「○○(テーマ)」について学ぶための授業。
それぞれのスタッフがどんなことをするか考え、それに参加したい人だけ参加する。
「教科別演習」…個別学習だけでは理解・定着しきれない部分を補うための授業。
学年に分けておこなう授業と、特定の教科について「これはマンツーマン/少人数でやったほうがいい」と判断しておこなう授業がある。
この定義に沿って、1学期に運営してきた「ゼミ」を、継続したり、解体してリニューアルしたり、新たにつくったりした結果、
ようやく2学期のゼミ・教科別演習の時間割が定まり、生徒一人ひとりに個別学習の時間割を決めてもらえる段階にたどり着いたのです。
1学期に生まれたもやもやが、議論を経て、少し晴れた!!というすっきりした気持ちも個人的にはある反面、
今回決めたこの定義が全てではなく、生徒・スタッフ関係なく、また誰かが新たなもやもやを抱えることがあれば、また議論をして、定義や枠組みを変え続けていく…
ということの繰り返しなんだろうな、という予感もしています。
でもそれこそが、学びの森の学びの森たるゆえん、なのかもしれませんね。
2学期からは、みんなでこれらの定義を共有しつつ、「このコマは何を学ぶ場なのか?」などの目的意識を持ちながら、
よりよい「学び」の形やあり方について考え、追究していきたいと思います。
定義ができたので、次は1回1回のゼミや教科別演習の中身を、試行錯誤しながらつくっていく段階…といったところでしょうか。
ああ、プレッシャー…いや、1からつくるワクワクを、みんなで楽しみたい!
ようやく涼しくなってきた季節の変わり目、学びの森の2学期がリスタートしたある日の、ながーいひとりごとでした。