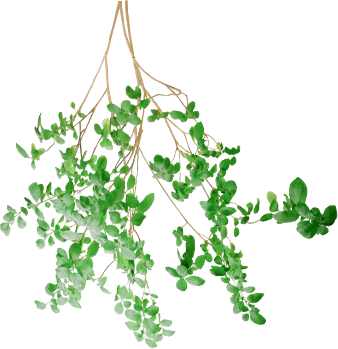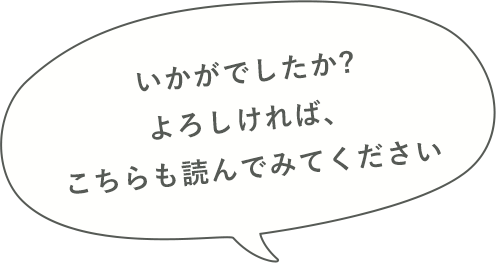話し合い
こんにちは、学びの森の樋口です。
学びの森では昨日(8月18日)から2学期が始まりました!夏休みは10日ほどでしたが、それぞれたくさんの思い出をつくって、存分に楽しんできたようです。
さて、2学期から学びの森では「スクールアセンブリ」という時間を新たに設け、話し合いの場を積極的に作っていきます。さっそく、昨日の5コマ目に小中学生に分かれて話し合いを行いました。
小学生のテーマは、「夏休みどうだった?」です。
旅行した場所や食べたもの、思い出などを順番に話し、それぞれが質問していきました。(「話し合い」と呼べるかは少しあやしいかもしれません…)
スタッフとして参加して感じたのが、普段のコミュニケーションとは異なる矢印や意識が生まれているということと、「聞く」という大切な土台があるということです。
普段は仲の良い友達と話すことがほとんどという人も、話し合いの場では、その場にいる全員に向けて話すことになります。
スタッフの問いかけに答えることから始まりますが、他の人から質問が出たら、それに答えることも必要です。
いつも一緒に過ごす人たちや、伝えたいことをくみ取り、様々な言葉を使って理解してくれるスタッフとの間では、安定した関係性があるので、全てを伝えなくても、「わかってくれている」という安心感があります。
しかし、少しその外に出ると、その安心感は薄れてしまうので、普段以上に「伝える」ことを意識し、理解する・されるための努力をする必要性が出てきます。
そのような努力をする練習の場として、話し合いは意義があるのではないかな、と思いました。
また、話し合いの大事な要素の一つに、「一人ひとりの意見をさえぎらず、最後まで聞くこと」があると私は考えています。
頭の中の記憶や思いを言葉に変換し伝えることが、得意な人も、苦手な人もいます。
また、話す人たちの関係性によっては、優位に発言できる人と、なかなか発言できない人に分かれ、結論に特定の人たちの意見が強く反映されてしまうこともあるでしょう。
学びの森にも、頭の中にある記憶や思いを言葉に変換し伝えることが、得意な人も苦手な人もいます。
積極的に発言する人もいれば、そうでない人もいます。
しかし昨日の話し合いでは、誰が話す番であっても、その人が話し終えるまで、できるだけ意識して耳を傾け、「聞こう!」とする姿勢を全員がもっているように感じました。
この姿勢を全員がもつことで、伝えるのが苦手な人でも、安心して話せる場がつくられていたのではないかなと思います。
子どもたちは特に、他の人の話を聞いて初めて出会う言葉や世界がたくさんあるので、話を聞くだけで想像するのが難しい…という現状はありますが、それでも理解しようとする姿が印象的でした。
話の中で、面白いエピソードが出てきたらみんなで笑ったりもするなど、和やかで実りある時間だったなと思います。また、自分の話がみんなに受け入れられるという経験が、子どもたちの自信にもつながっていたらよいなと思います。
学びの森に少しずつ変化の波がやって来そうです…が、変化をおそれずに、なくなるもの・新しく生まれるものをきちんと見据えながらやっていきたいと思います。2学期もどうぞよろしくお願いします。