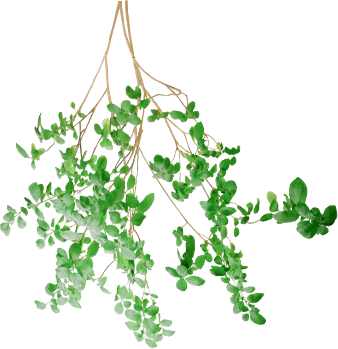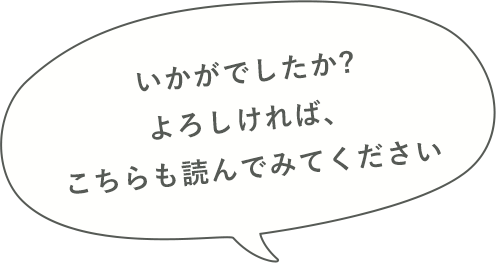1学期最終日
ご無沙汰しております、学びの森のキノシタです。
今日は最終日ということで、午後から<探究報告会><1学期の振り返り><2学期の作戦会議>を行いました。
早速どんな様子だったのか見ていきましょう!
まずは探究報告会。
小学生3名と中学生2名が、それぞれ自分で決めたテーマについて調べたこと、作ったことを発表してくれました。
①小学6年生Aくん
テーマ:「マグマができる理由」
得意の絵を活かして、マグマができる理由や噴火の流れ、火山にまつまる豆知識などをまとめて報告してくれました。
作った資料は情報がびっしり!
そういえば亀岡図書館や府立図書館に行ったときも、このテーマを調べるための本を借りていたのを思い出しました。
また、資料は調べた内容と漫画が融合していて、飛び出す、動き回る、躍動感のある、全く新しい図鑑のよう!
生徒からは、絵が入っていてわかりやすい!ここまで自分で編集できるってすごい学びになってると思う!という感想が。
Aくん自身も「最初調べようと思っていたことから、どんどん疑問や発見が出てきてまとめるのが大変だった」と、深まり広がるプロセスを語ってくれました。
②小学5年生Bくん
テーマ:「魔女」
魔女という概念が出てきた歴史について、文章にまとめて報告してくれました。
Bくんの調べでは、「魔女」という概念は時代によって変化しており、中でも15世紀以降には、ある種の差別や迫害と結びついて「魔女狩り」が行われた経緯があるそうです。
難しいけど考えるべきテーマがたくさん詰まっているように感じました。
また発表までに、王先生と一緒に文章化に取り組んでいるBくんの姿が個人的に印象深かったです。
「まず魔女とは何かを定義しないと伝わらないんじゃない?」や「この言葉はどう説明するの?」と王先生に突っ込まれることで、Bくんの思考が少しずつ形になっていく感じが伝わったからです。
本人も今回の文章にまだ納得はいっていないようなので、今後もっとブラッシュアップしてほしいと思いました。
③小学5年生Cくん
テーマ:「折り紙の攻略法」→「京都駅の歴史」
Cくんは途中まで自分が普段やったことがない「折り紙」に挑戦していました。
ただ折り紙を折るだけではなく、折り紙が苦手な人でも折ることができる「攻略法」を考えようとしていたみたいです。
折り紙が大の苦手で、折り方の図がさっぱり頭に入ってこない(図を載せる意味あんのか?!とすら思う)僕のような人を救うテーマでした。
ただ残念ながら、その方法を言葉や絵などなんらかの形でまとめるのが難しく、テーマを変更したという報告にとどまり、本人も複雑そうな表情。
「なんらかの形にして発表する」というハードルは決して低くはないかもしれませんが、これに懲りずそのプロセスの難しさや楽しさを経験してほしいと思いました。
④中学2年生Dくん
テーマ:「47都道府県の紹介」
Dくんは地理や建物が好きなこともあり、みんなに各都道府県のおすすめスポットをまとめてくれました。
発表を聞いているうちに、Dくんの裏テーマが「みんなを笑わせる」であると感じられました。写真やコメントが「ボケ」で、見ている我々が「ツッコミ」みたいな構図です。
みんなが笑ってくれたときの嬉しそうなこと!逆にウケなかったときのしょんぼり感!
こういう形でみんなとコミュニケーションを取ることが、Dくんにとっての<探究>なのかなと思いました。
で、あるとすれば、もっともっとその「笑い」を追求してほしい。
Dくんには、「笑い」をつくるって生半可なもんじゃないと敢えて伝えたいなと思いました。
⑤中学1年生Eくん
テーマ:「Scratchでゲームを作る」
小学6年生からこのテーマに取り組み続けているEくんは、流石の一言。
昨年度よりもディティールやギミックにこだわってゲームを作っている感じがしました。
だからこそ自然と「やりたい!」とみんなが集まっていきます。
こんな風に、誰かが楽しめるものをプログラミングを駆使して作ることができるってすごいことだなぁと感心していました。
Eくんはもともと、好きなことはとことんタイプだと感じるので、今後もとことんこだわってテーマに取り組んでほしいなと思いました。
<探究報告会>の様子はこんな感じです。
ほとんど僕の感想になってしまいましたが、少しでも伝わればと思います。
では次は<1学期の振り返り>と<2学期の作戦会議>の様子をお伝えします。
<1学期の振り返り>は、小学生と中学生を分けて行いました。
小学生は久保先生と樋口先生、中学生は亀谷先生と王先生と米井先生も入っての話し合いとなり、僕はいったんフェードアウト(一部の生徒にとっては僕がその場にいない方が話しやすいらしい!あかんやん!笑)。
写真を撮るついでに教室をのぞかせてもらったのですが、みんな素直に安心して色々な意見を出し合っている印象を受けました。
中学生はそれに加えて「落ち着いてじっくり考える」ことも含まれていたように思います。
こういう雰囲気ってどんな経験の積み重ねの中で生まれるのかなぁとしみじみ考えたりしていると、もう15:30!!←実は報告会が押してしまいました…。
<2学期の作戦会議>では、振り返ったことを全体でシェアしているうちに時間は過ぎていき、作戦会議は文字通り2学期に繰り越し。笑
この辺りはまた他のスタッフにブログで紹介してもらいましょう!
作戦会議の入り口として、生徒たちには二点だけ、今後の方向性を提案しました。
一つ目は、こうしてみんなで話し合う時間を学びの森の時間割に組み込むこと。
イベント、遠足・合宿、時間割、学習の計画・方法、約束事、ちょっとした疑問や提案など、学びの森に関わることをみんなで、あるいはユニットで話し合う<スクールアセンブリ>という時間を設けたいと考えています。
これまでは「みんなで一緒につくる」と言いつつ、お互いの意見や考えをじっくり話し合う時間が取れていませんでした。
だからスタッフと生徒の間でズレができたり、主体性は誰にあるの?という議論が出てきたりしていたように思います。
そういった時間を時間割に組み込む、つまり「当たり前」にすることで、ちゃんと「一緒につくる」ことができたり、二つ目に伝えたことにもつながると考えました。
その二つ目とは、学びの森の活動の一つひとつをつなげて「ストーリーをつくる」のを意識すること。
これは僕自身もまだこれから試行錯誤の段階なのですが、これまでは個別学習やゼミ、教養講座で取り組んでいる内容とイベントや遠足・合宿や学びの森の内外での日常が切り離されていた感じがします。
だからその時その時で活動を「消費」してしまっているような、「単発」で終わってしまっているような感じがあったんだろうと思います。
だから今後は、それらをつなぐストーリーをつくる、つくろうと意識することが大事なんだと思うんです。
なぜこんな風に考えるようになったのか、それはここ最近、ある生徒が学びの森にやってくる前から現在までの振り返りを文章化したこと、それに影響を受けて(ここは僕の仮説)またある生徒が小学生のときに受けた道徳教育に対する疑問点を文章化したこと、その文章をもとにことばゼミで各生徒がそれぞれに問いを立てて考え始めたこと、という一連のストーリーが生まれたからでした。
こうしたプロセスを生み出すために、あるいは展開していくためにも、自分がストーリーをつくる意識を持って、その時々に自分がなぜ・どうやって関わるのかを考える必要があるし、そこにこそ「学び」があると考えました。
とまぁ、なんか2学期も面白くなりそうな気がしています!
生徒や保護者の方々、スタッフの方々、関わってくれた皆様、1学期お疲れさまでした!
2学期からも何卒よろしくお願いいたします!
では、また~