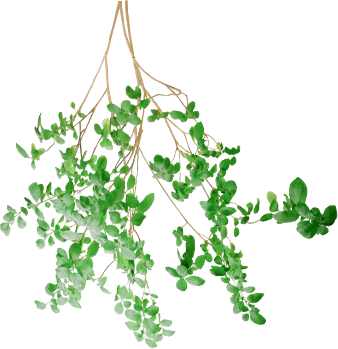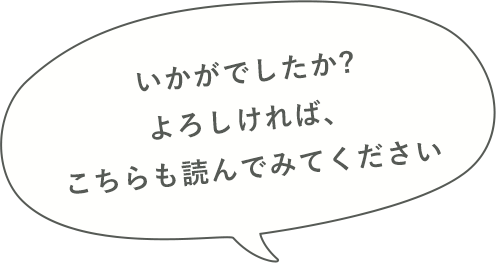何を学んで欲しいのか?
こんにちは、学びの森の王です。
放課後等デイサービスの方の子どもたちはすでに夏休みに入ってるのですが、フリースクールの夏休みはまだ少し先のようです泣
最近あまりブログが書けていませんでしたが、この間で考えていたことを言葉にしてみたいと思います。
最近、生徒に「何を学んで欲しいんだろう?」と考えることがあります。
これは、個別学習の中で感じていたことがきっかけです。
算数があまり得意ではない小学生が、算数の時間に席を立ちうろうろしてしまう。
それに対して、スタッフが指摘する。
あんまりやりたくない理由があるのかどうかを聞くと、「2桁×2桁の掛け算がわからない」と答えていました。
それをみて自分も、「確かにあれは定着するのに時間がかかりそうだなぁ」と思っていました。
現在その小学生は、算数の時間にはスタッフと一緒に取り組むこととなっており、少しずつ自信をつけてきたように思います。
このような場面を見て、自分の中では少しモヤモヤが残ってしまいました。
個別学習(学習指導要領に沿ったもの)は基礎的な能力だから、身につけなければならない。
スタッフと一緒に取り組むこと自体、間違ったことではない。
自信をつけてきたのは良いことのように思う。
ただ、これは上記の小学生に限ったことではないような気がします。
他の小学生によく見られるのは、「分数の計算がうまくできない」というもの。
それに対して、スタッフも計算方法のコツを教えますが、意外と小学6年生の分数の計算は厄介で、とても時間がかかるものです。
しかし、自分が中学1年生と中学3年生の数学のゼミを担当している中でも、小学6年生のような分数の計算は出てきません。
そうなると、小学生に「何のために分数の計算をこんなにがんばらないといけないんですか?」と聞かれた際に、うまく答えられないような気がします。
他の選択肢として、分数の計算をもし電卓アプリやチャットGPTを使って正確な答えを出せるのであれば、それはそれで1つの重要なスキルなのではないかと感じます。
子どももモヤモヤし、スタッフもモヤモヤし、、、結局彼らに何を学んで欲しいのかを問われているような気がします。
そして、それを考える上で「優先順位」がポイントになるのではないかと感じました。
子どもが教育の場にいられる時間は限られています。
その限られた時間の中で、何を学ぶのか。
社会に出た時に、どのような知識やスキル、経験が身についていれば、自分で判断し、決定し、動くことができるようになるのか。
いずれは一人暮らしをするとする。そのときに必要になるのは、不動産や賃貸に関する知識、相場の感覚、、、あるいは、料理のスキル。
仕事をする時には、わからないとことは自分で調べて身につけることも必要になってくる。
それらは5教科と比較すると、教育現場であまり焦点が当てられていない部分でもあります。
5教科が必要ではないとは言えない、ただ優先順位を考えた時に、「これは学んで欲しい」というものが、5教科以外にあるかもしれないなと思いました。
では、その優先順位は大人が子どもの考え抜きに決めていいものだろうか、、、
ただ、子どもはそもそも何を学ぶべきかを判断できるだけの経験を持ち合わせているのだろうか、、、(小学生と中学生でも違うと思います。)
ということをぐるぐると考えている今日このごろです。
これは、学びの森で行っている教養講座にも関連する議論かなと思います。
直近ではお金に関する教養講座がありますが、それを生徒たちはどう受け取るのか、楽しみです。