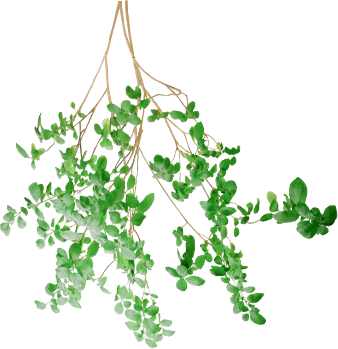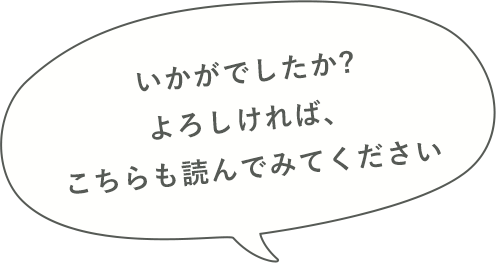「話を聞いてくれる先生」
こんにちは、学びの森の樋口です。
私は最近、「先生の役割って何だろう?」ということをよく考えています。今回はその中の1つ、「話を聞いてくれる先生」について書いてみようと思います。
…とはいっても、そもそもなぜ、そんなことを考え始めたのか?
きっかけは、私が学生時代に参加していたボランティア活動にあります。
その活動は、子どもたちとボランティアが一緒に遊んだり、ご飯を食べたり、話を聞いたりして、ゆったりした時間を過ごすというものです。ボランティアは、子どもたちのやりたいことに付き添い、話を否定せずに聞き、子どもたちと一緒に楽しく過ごすという役割を担っています。
今振り返ると、ボランティアとしての関わりの中でいちばん大切なことは、「話を否定せずに聞くこと」だったのだろうと思います。
ボランティアは、子どもたちがどれだけきつい言葉を言っても、道徳的にどうなんだ?と思ってしまう行動をとっても、それを注意したり、止めたりするようなことはしない、というのが原則でした。(蛇足ですが、そのような言動をとる子どもたちには、一概に注意したり、厳しく接したりすることが難しい、複雑な背景があります。)
この原則を掘り下げて考えると、「子どもたちが安心して、自由に自己表現できる場をつくる」という目的のためにあるのではないかと思います。そして、そのような場をつくる上でもっとも阻害となるのは、「大人からの否定」と「大人が定めた枠組みを子どもたちに押し付けること」です。
だからこそ、ボランティアは注意するようなことは何も言わず、子どもたちのことを受け止めることが大切だったのだろうと思います。
さて、「子どもたちに関わる大人」というくくりにおいてはボランティアも先生も同じですが、その立場はかなり異なります。「先生」として約4カ月働く中で強く感じるのが、話を否定せずに聞くことの難しさです。
もちろん、「先生の考えが正しくて、子どもたちの考えが間違っているから、子どもたちの話は聞かず、正解を教えればよい」などといった考え方は一切持っていません。ただし、「子どもたちの考え方そのものが間違っているわけではないけど、そのままでは将来困るだろうから、大人から別の見方を伝えた方がよいな」と思うことはあります。
一方で、大人の立場から別の見方を伝えると、子どもたちは間接的に「自分の考え方は間違っているんだな」と感じてしまうかもしれません。また、大人の見方を受け容れられるかどうかは、子どもによります。このため、意見を受け容れることが難しいと、「否定された」と感じて、大人に対して攻撃したり、殻に閉じこもってしまったりすることもあります。
ちなみに、子どもたちが大人の考え方や価値観を受け容れることが難しい理由として、言葉のニュアンスの問題があるように思います。
日本語では、「違う」という言葉に、強烈な否定のニュアンスが含まれているように感じます。「それはそれ、これはこれである」と区別する意味での「違う」と、「どちらかが正しく、どちらかが間違いである」という意味での「違う」、どちらも同じ言葉なのに、後者の意味合いで受け取ってしまうことが多いように思うのです。伝わり方を考慮すれば、前者の「違う」は、「異なる」と表現する方が適切かもしれません。
ところで「先生」は、考えたり表現したりすることを通して、子どもたちが様々な見方を知り、自己の幅を広げていく手伝いをする「ような」(←自信がないので強調しておきます!)役割があるのではないか、と私は思います。だからこそ、子どもたちに伝わらない、拒否されるリスクを冒してでも、伝えるべきだと思うことは、「先生」という仮面をかぶって伝えなければならない場面があるように思います。
こう考えると、子どもたちの「話を聞」き、安心して自由に自己表現できる場をつくることと、「先生」として伝えるべきことを伝える立場を両立させ、「話を聞いてくれる先生」で在ることは、実は絶妙なバランスの上に成り立っている、という結論に至ります。
…あーー難しい!難しすぎる!
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。悶々と考える日々が続きますが、暑さに負けず、子どもたちにも負けず、頑張ろうと思います。