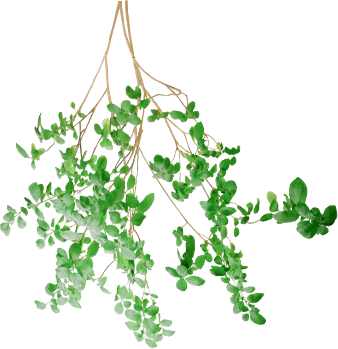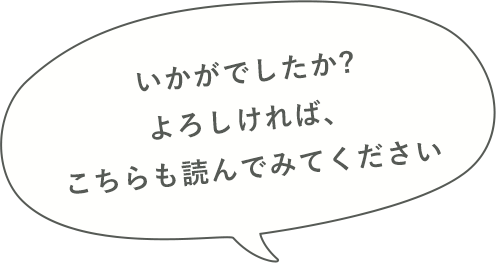<ゼミ>って何なん?
どうも、学びの森のキノシタです。
今日は活動のひとつである<ゼミ>にまつわるエピソードをご紹介します。
学びの森では、生徒たちと話し合いながら<時間割>をつくっています。
その際、小学生には理科の実験やフィールドワークの<ゼミ>があったらいいかなぁ、中学生には広い意味で「ことば」を突きつめて考える<ゼミ>があったらいいかなぁ、受験生にはガッツリ問題演習ができる<ゼミ>があったらいいかなぁなど、こちらがいくつか<ゼミ>という枠をあらかじめ設定しています。
実はこの<ゼミ>という形で学ぶ時間は、桜井先生が学びの森に来てから始まったんです。
それまでは高校生がたくさんいて、それぞれに必要な学習を個別で取り組む形しかありませんでした。
そこに、ひとつのテーマについて他者と一緒に考え合うような形が生まれました。
その目的は、「教師-生徒」における「教える-教えられる」という関係を変えることです。
言い換えれば、教師が一方的に何かを教えるのではなく、生徒と共に問いを持ち、考え学び合う時間・空間をつくることだと言えます。
そんな時間や空間をつくるために、この10年くらい試行錯誤を続けてきたわけなんですが…。
ある生徒が時間割をつくっているときに、「ゼミ多いな」とつぶやきました。
そんな多かったっけ?と思いながら手元の時間割を見ると、ゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミ。
ゲシュタルト崩壊しかねないほど大量にゼミの文字が。
あ、これはあかんかも。と直感的に思いました。
僕の中でいつの間にか<ゼミ>を時間割に入れるのが当たり前になってしまっていて、それがどんな目的で、参加している一人ひとりにとってどんな意味があるのかをすっ飛ばしていたことに気が付いたんです。
やっぱりそもそも<ゼミ>が何をするための時間なのか、改めて生徒もスタッフも一緒に考える必要がある。
そういった問題意識をみんなに伝え、今少しずつそれを話し合っています。
面白いことに、そうやって問いを投げかけると、みんな真剣に考えてくれています。
・扱う問題が難しいから、別の時間にもっと基礎的なことを学習する時間をつくりたい
・何か身近なテーマについて、みんなで考え合う時間は毎日あってもいい
・個別学習の時間を増やしたい
・みんなで一緒に、協力して何かをやり遂げるような時間があるのって大事
などなど、これまでこちらが勝手に振り返って考えていたことに対して、それは同意できる、それは違うという意見をくれました。
その結果、お互いにこのゼミに参加する意味を改めて確認することができ、これからの方向性や具体的に取り組む内容も一緒に考えることができました。
このエピソードを通して、反省しないとなぁとしみじみ思いました。
「時間割は一緒に考える」と言いつつ、ゼミについては「当然参加するもの」と、今ある枠そのものを問い直せていませんでした。
だからお互いの熱量や参加の仕方にズレが生じたり、それぞれに意味を見出せないことにつながったりしたのかなと思います。
学びの森における「学び」の特徴というか、大事にしたいところって実はここにこそあるのかもしれません。
―何をどのように学ぶのか?またなぜそれを学ぶのか?
自分にとって/お互いにとって学ぶ「意味」を、言語化したり感覚的に身体に落とし込むプロセスをしっかりと踏む。
その積み重ねが大切だし、僕自身が続けていきたいことなんだと思いました。
まだまだ問い直していきたいことがあるなぁ。
焦らずじっくり、みんなで考えていきたいと思います。
では、また~