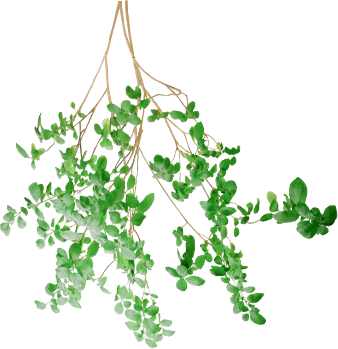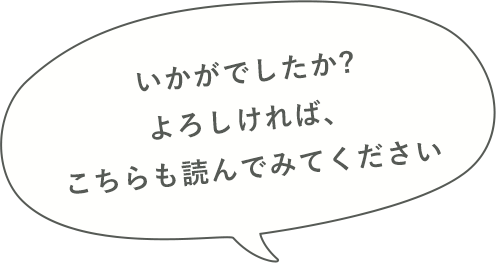自分で決めることの意味
こんにちは、亀谷です。
桜満開シーズンが過ぎ、気持ちの良い気候になってまいりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
私はまだまだ花粉症に悩まされておりますが、(花粉なのか黄砂なのか、、)
少しずつ気温が上がってきたので、ようやく冬の寒さから解放されることにホッとしております。
自宅横の農業用水路に、今朝から水が流れ始めているのに気付き、
今年もこの季節がやってきたか、としみじみ。今年も稲作のスタートです。
さて新年度がスタートし、学びの森も新たな雰囲気を感じているところですが、
新たな雰囲気ってどんな雰囲気?
まず一つは新しいスタッフが2名加わったこと。
王先生と樋口先生です。以前からこちらに関わってくださっていましたが、
今月から正式に常勤スタッフとしてスタートを切られました。
それからゼミ室が増えたので、個別学習の場所が1階と2階に分かれていること、
約束ごとを改めて全員で確認し合意を得たこと、
などになるかと思いますが、
私自身も新たな気持ちで臨みたいと思っていることも一つあるかなと思っています。
先月末で前の学年が終わり、今月から新しい学年、ということを、
生徒自身は特に自覚はない、と言いつつも、
やっぱり意識は異なるものがあるようにも感じるのですが、
不思議なものですね。。
卒業式なども同じく、何も目に見えるものはないけれど、
気持ち的になにか違う。
これは無理やりそういった型にはめようとしているからなのかもしれないし、
それが学びや成長とどう関わってくるのかも気になるところではありますが、
先日の卒業式でも出てきた「節目」というキーワードにもつながるし、意味のあることだとも思います。
そして私自身もこちらで働くのが4年目に入りましたので、
そういった意識がありますし、
改めて生徒たちとどのような関りをするべきなのかを問われている、という気がしています。
今自分の役割は何なのか。
生徒たちがより<自律>に向かうためにどのような役割を担うのか。
そしてこれを考える前に、
生徒それぞれがどんなことを考えているのか、
何をどんなふうに学びたいのか、
あるいは何に困っているのか、などを知ることが当然必要で、
その前提として、生徒自身からこれらのことについて発信してもらうことも必要になるとも思っています。
今は言葉にならなかったり、自分でもよくわからないことかもしれませんが、
そこはもちろん自分ごととして考えたり、問い続けてほしいと思います。
私自身もどうしたらいいか全然わからないときや、自分では決めきれないときなんかはしょっちゅうありまして、
その時々でいろんな人に相談したり、意見を聞いたり、
関わっている相手とお互いに意見を出し合って決めたりしています。
そうやって「自分なりの答え」を都度出しながら進む、といった感じです。
生徒それぞれにおいても、なんでもいい、どっちでもいい、などにとどまらず、
最終的にはやっぱり「自分が決める」ということがとても重要になってくると思うので、
一緒に考えながらサポートしていきたいと思います。
この作業そのものが<自律>に向かっているのではないか、とも思います。
また、昨日新たに入ってこられた樋口先生の<語り場>があったのですが、
その中に「あ、似たような感じ」と思ったことがありました。
樋口先生は大学で福祉について学ばれる中、「<自立>を目指した支援を」することが福祉の理念にある、と学ばれ、
「人間は、完璧になることが理想なのか?」と問いを立てられたというお話を聞きました。
それと関連するなぁと思ったのです。
(自立と自律の違いについては別途議論が必要になるかと思いますが、今はおいておきます)
自分で考えて自分で決めたり、自分で判断していくことが増えるのは望ましいことかもしれないけれど、
全部自分だけで決めたり、全部自分だけで判断しないといけないなんてことはないよな、
まわりの人の助けに支えられることは、<自律>してないわけではないよな、
と思いました。
私の中で、どこか、「人を頼らずに自分で解決せねば。甘えてはいけない。迷惑をかけてはいけない。」といった
考えが自分の中にドカッと居座っているように感じていたからです。
(これだけ人に迷惑もかけて、支えられておいて何を言ってるんだ、と
一方では思うのですが、その不甲斐なさに折れそうになることもよくあるので)
とはいえなんといっても、誰かが正しい答えを示してくれるわけではないので、
やはり自分の納得のいくように、
自分の判断にしっかり向き合えるように、自分で決断していくことの意味は大きいと思いますので、
学びの森の参加者として、生徒本人がどのように参加したいのか、
同時に私自身はどのように参加したいのか、ということを考え、
またシェアしていけたらいいなと思っています。