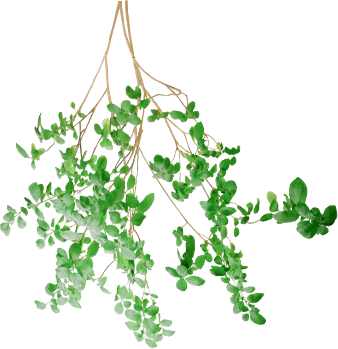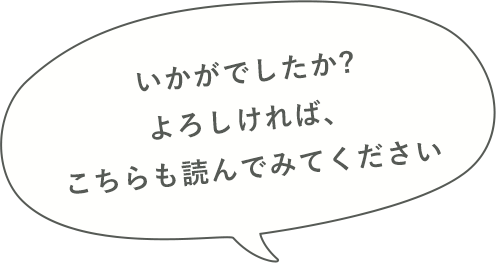卒業生の語り
どうも、学びの森のキノシタです。
高校入試説明会に保護者面談、教養講座と、1~2月は怒涛のように過ぎ去っていきました。
そして3月もまた、気が付けば半分以上過ぎていると…。きゃー
学びの森も、いよいよ1年の締めくくりである「卒業式」を控えるのみとなりました。
卒業式に先立ち、卒業(予定)生にこれまでを振り返ってもらう機会を設けました。
今年度の卒業生は小学生が3名、中学生以上が3名の計6名です。
こちらが投げかけた質問は、
①学びの森で1番印象に残っている出来事は?
②学びの森に来たときの第一印象は?(代表の第一印象も!)
③自分が来たときと、今の学びの森って雰囲気違う?
④学びの森にきてから自分が「変化」したと思うことってある?
ざっくりこの4点。
これらに対する卒業生の語りから僕が考えたことを書きたいと思います。
まず、①について圧倒的だったのが「合宿」について。
同じ部屋の人と3時間ずーっとUNOをし続けた(終わらなかった)こと、テンションが上がって寝られなかったこと、そのせいで次の日しんどすぎたこと―。
みんな口々に、日帰りの遠足やフィールドワークでは得られない、合宿ならではのエピソードを語ってくれました。
じゃあその経験の意味って何なのか?
卒業生の語りからは、具体的な活動内容というよりもむしろ「合宿」という経験そのものに意味がある、という印象を受けました。
経験してきたことが「違う」人たちが集まり、日常とは「違う」状況で、家(家族)と「違う」リズムで、「同じ」時間や空間、「同じ」身体感覚を、一瞬でも共有できる。
つまり、異質な者同士が異質であるという前提のもとに、その瞬間出会い、共有部分を一緒につくる/つくろうとすることが、生徒たちにおける「合宿」という経験なのかもしれません。
本来違うことが前提にあるはずの個人に対して、同じことを同じようにすることを求められる学校という枠組みに合わなかったり、はみ出した子どもたちが、改めてお互いの「違い」を認識しつつも、「違い」があるからこそ「同じ」を共有することの喜びや難しさを経験することが、これから社会に出ていくときに必要だという意味付けもできるのかなぁと。
②と③の質問に対する卒業生の語りもまた、この考えを裏付けるものであったと思います。
学びの森に長い期間通い続けてくれた卒業生にとって、最初に来た時と今ではずいぶん学びの森の雰囲気は違ったようです。
昔は中高生が多く、小学生は2,3人しかいませんでした。
学習もゼミのような形式は少なく、ほとんどが個別学習で、時間割もスタッフが決めていました。
その子によれば、昔の学びの森はどちらかといえば「一人ひとりが自律的に学ぶ」という色が強く、それゆえ「お互いに交わらない/交われない」雰囲気もあったと。
それが徐々に小学生が増え、今ではほとんどが小学生という状況に。
そうなり始めて、より「一人ひとりが自律的でありながら、共同で学ぶ機会もつくる」という雰囲気ができあがってきたとのことでした。
もちろんまだ完全に実現できているわけではありませんが、その生徒が感じ取った変化と、僕がここ数年意識してきたこととが重なっているのが面白いなぁと思いました。
そういった学びの森全体の変化が関係しているのか、④について「他者と関わることに対する自信がついた」という意見も多く出てきました。
具体的には、
・もともと人と話すのは苦手だったけど、今は色んな人と話せるようになった
・集団で何かをすることが苦手だったけど、自分なりの役割や居方を見つけることができた
・自分ではそうは思わないけど、新しいことに挑戦するようになった
などです。
その中で1人、「特に変わったところは思いつかないかなぁ」と言う生徒がいました。
僕が他の生徒に「○○くんの変わったところってあると思う?」と聞くと、その生徒も「小さい頃からずっと一緒やけど、小3の頃のままって感じ」と返ってきました。
スタッフからも「こういうところは変わったかもしれないけど、良い意味本質は変わってないのかなと思う」という意見も。
これらの意見を聞いたときに、僕の中でハッとしたことがありました。
学びの森では「変化」や「変容」という言葉をよく使いますが、それらの言葉にはあるイメージがすでにくっついているような気もします。
そのイメージは、どこか時間の経過とともに右肩上がりにより良くなっていく―みたいな。
「成長」とか「発達」とかも同じような類の言葉かもしれません。
でも本当にそうなのか?
もっと立体的に、前にいったり後ろにいったり、ぐるぐる回ったり、いきなりギュイーンと上がったり下がったり…。
その総体を「変化」という言葉は包含しているはずなのに、いつの間にかひとつのイメージを持っていて、そのイメージに価値を置いている自分はいないか?
もう一度その辺りを考え直して言葉を使う必要があるよなぁと反省しました。
いや~、でもみんな自分の言葉で語るようになったなぁと本当に感心しました。
なんでこんな語れるようになるんやろう?
語れるようになるってどういうことなんやろう?
卒業生の語りから、また僕の問いが広がりました。
少し早いですが、卒業おめでとうございます、あと語ってくれてありがとうございました。
この後開催された「卒業生を送る会」の様子は亀谷先生のブログにバトンタッチします!
皆さま乞うご期待!
では、また~