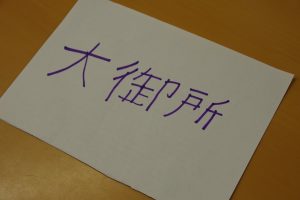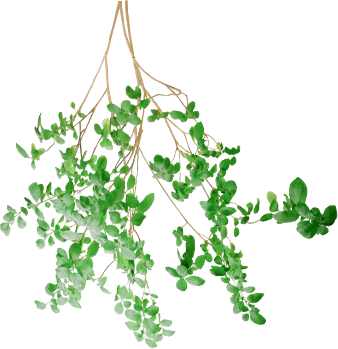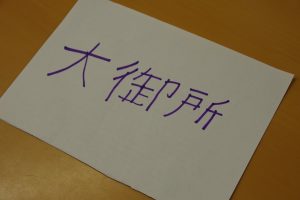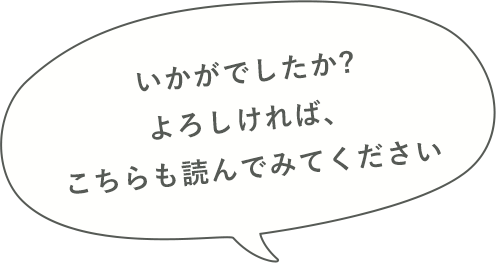こんにちは、亀谷です。
ようやく春めいてきて、世間も卒業、修了のシーズンになりましたが、
学びの森の卒業式は3月25日、明日!早いです( ゚Д゚)
それに先立って今週火曜日に、卒業生の語り場に続き、卒業生を送る会を開きました。
中高生が協力していろんな準備をしてくれたこともあって、
とても楽しい会にすることができました。
ちなみに去年は「卒業生が送られる会」ということで、
卒業生による企画運営のお楽しみ会をやりましたが、
今年は、卒業生も在校生も企画運営側になり、中高生全員で準備する形をとりました。
今回も新たな挑戦があったので、
無事に実施することができてよかったと思っています。
まだ生徒と振り返りをしていないので、
みんなの感想も聞いて振り返りたいと思っていますが、
当日を迎えるまでの様子も交えてお伝えしたいと思います。
今年もこのシーズンが近づいてきたので、
中高生に今年の送る会はどうするか、1か月ほど前に話し合いの場を持ちました。
その中で、卒業生も含め、「思い出を作るためにお楽しみ会をする」という意見で一致。
さてそれでは、だれがどんな企画運営をするのか、いちから決めていく作業が始まりました。
実は初め、だれが中心となって決めていくのか、実行委員を決める?といった話もなかなか進まなかったんです。
卒業生の中には、自分が企画側にいってもいい、と言ってくれていたのですが、
その他の生徒は「えー」みたいな反応だったので、私も正直に、
「思い出作りのためにお楽しみ会をやろう、と合意しておいて、その反応はちょっと卒業生に対して失礼なのでは、、」と伝え、
なかなか本心を出せていないのかもしれない、とも思ったので、
今の考えというか、今の気持ちを彼らに書いてもらいました。
すると、ほとんどみんながこのようなことを書いていました↓
・お楽しみ会自体はやりたいけど、人をまとめたりすることは自信がない。
・人前に出たり、意見を言うのはちょっと遠慮するけど、何かできるのであればやります。
・主体となってやるのはキビシイけど、サポートならやれます。
・今ちょっと勉強がんばってて余裕がないので、何か手伝うくらいならできるけど、、
そうか、、そういうことやったんか、と気づくことができました。
ならばどうしていこう。
もうこのままみんなに問いかけました。
卒業生の中で、企画側になってもいいと言ってくれていた生徒には、
総合的な企画側になってもらい、主にこの生徒と一歩ずつ進めていくことに。。
まずは、「お楽しみ会をする」ということであれば、プログラムとして何をするかは全員からアイデアを出してもらおう、
ということになり、みんなに考えてもらいました。
すると、クイズ大会、人狼、宝探し、各種ゲーム、みんなでドッジボール、などのアイデアが出てきたのですが、
さまざま話し合った結果、クイズ大会と宝探し、で決まりました。
それではクイズ大会と宝探しについて、自分は何を担当したいか、という話し合いをして、
役割分担をしていきました。これが意外とスッと決まり、具体的に準備開始!
すると担当者の中でどんどん話が決まっていき、壁にぶつかりながらも、
「ほなどうしよ」「そしたらこうしよ」といった感じで進んでいくので、
今振り返ってもみんなすごいな、と思っています。
転がりだすと早い、という感じで。
今回もクイズ大会を担当してくれるだろうとふんでいた生徒たちが、
クイズだいぶやったからネタが尽きた、と言って宝探しの担当を希望したり、
あまり大きな役割を担うのはちょっと余裕がない、と言っていた生徒がクイズの出題者になってくれたり、
前に出るのは自信がないけど、それ以外はやる、と言ってくれていた生徒が、
宝探しのルールなど詳細を率先して考え、宝探しチームのまとめ役を自然と担ってくれていたりと、
こちらの予想外だったり、予想以上の姿を見せてくれました。
生徒たちからしたら、「いや、この状況でもうNoは言えへんやんか」と言われそうですが、、(^^ゞ
また、これまで全体の行事のときにちょっと消極的だった生徒も、
あるクイズを提案し、企画側に立ってやり遂げたことも大きな挑戦であり、ひとつの達成となりました。
あるクイズというのが「格付けクイズ」。
初め、このクイズではどんなことをするのかを聞いて、
すごくおもしろそうで、即「やろう!」と決まりました。
水の飲み比べでは、亀岡の水道水(学びの森の水道水)と、
市販の天然水を飲み比べて、どちらが天然水かを当てるというクイズと、
マグロとカツオの食べ比べでは、
それぞれを食べて、どちらがマグロかを当てる、
ということで、私自身もすぐにイメージできました。
ところが、これを提案した生徒と一緒に、
どんなルールにするのか、どのように進めるのか、などを確認していくうちに、
テレビ番組でやっている芸能人の格付けチェックを模して、できるだけ忠実に再現したいということがわかってきました。
ほぉ、なるほど、と思うこともあれば、
これを学びの森で実施するにあたって、どうなんだろうか、と悩んだ部分もありました。
というのも、この格付けチェックという番組は、
私も部分的に知っているだけでしたが、
芸能人をまさに格付けする、ランクをつける、というシステム、
違いの分かるものが上位ランクになれる、
違いの分からないものはランクが下がり、
最終的にはテレビに映れない、というルール。
それがエンターテインメントの世界。
はい、それは理解しています、が、それを学びの森に持ち込んでいいものか、、、と。
総合的に企画側になってくれた生徒とも一緒に考えました。
正解したから間違えた人より上なの?
正解したからマウントとったり、笑いものにしていいの?
いやこれはあくまでもゲーム、それがお互い承知の上で楽しむ分には問題ないかな?
3人で数日間かけて話し合い、
そして全体に対して2度アンケートをとりました。
結果、もちろんあおったりからかったりは当然しない、
最下位になっても罰ゲーム要素は無し、
ということで実施することに決定。
提案してくれた生徒も納得し、当日も大変盛り上がった企画となりました。
そして「宝探し」も今回のもう一つの挑戦でした。
宝探しも、箱作り担当、ルール考案とポイント担当、隠しに行く担当、などきちんと分担し、
それぞれの持ち場をやりきりました。
そしてこれの大きな要素は、近くの公園で実施するということ。
幸いお天気も良く、準備も間に合ったものの、
やはり初めてのことなので、
現地の状況など見て、時間的なことやルールなど各々が考えて行動する場面も多々ありました。
そこで機転を利かして実際に動いてくれたおかげで、スムーズに運び、
参加者もやりごたえのある企画となり、
また次につなげていける発見もありました。これもすごかったです。
そして、これらの件を通して起こっていたことにも、
私としては大きな変化というか、大きな意味があったのではないかと感じていることがあります。
まずは格付けを提案してくれた生徒が、当日を迎えるまでの準備期間に、
これまでにない積極的な関わりを見せてくれたこと。
今回は、必要なカードを自分で作ったり、
宝探し用の箱作りを手伝ってくれたり、
当日には、天然水を買いに行ってくれたり、と
本当に前向きに行動に移してくれました。
そして総合的に企画側になってくれた生徒が、
親身になって話を聞き、どうすれば可能な限り彼の
希望に沿って実施できるかを、文字通り向き合って、真剣に関わってくれたこと。
そしてこの総合企画側の生徒にとっても、
以前は人に話しかけることもけっこうなハードルだったとのことですが、
何を話し合うのか、どこに向かっているのかが、
明確にあることで人と関わりやすくなったのではないか、と感じているようです。
理解し合うとか、考えをすり合わせていく、という作業の中で、
喜びといったら大げさかもしれませんが、
うれしさや安心感も感じることができ、この感覚を共有できていたらいいなと私としても思っています。
特定の生徒に限らず、それぞれにここからまた一歩先の、新たな景色が見えてきたらいいなと思います。
そして改めて、シンプルなことなんですけれども、
やってみないとわからないもんだなぁ、と気づかされております。
これまで、自分が提案したり、自分のイメージでアドバイスすることが当然多かったわけですが、
今回は、実施日に間に合わさないと!という意識ももちろんありつつも、
それよりも、こうやってみたらどうなるんだろう、という姿勢で、
じっくりと向き合ったり考えたり、任せっきりにしたり、を意識的に取り組むという結果になりました。
そこからやっぱりやってみないとわからないということを感じました。
できないと決めつけているのは誰なんだろう、
できそうだしやってみよう、と思うポイントって何なんだろう、
できると想定していたことも、実際の現場ではそうはいかなかったりすることもある、
それでも楽しいって思えるって何なんだろう、
など改めて考えさせられております。(普段の教科学習においても)
そして最後に、
昨年度から中高生の活動をスタートして丸二年、
行事では自分たちで企画運営をする、ということを
経験してきたということに、
今回彼ら自身が何かをつかんでくれている気がします。
それぞれに何かできることをやろうと、
関わろうとしてくれていること、
それが単純に楽しく、盛り上がってきたぞ、につながっているのではないかなと。
引き続き考えたいと思います。
今年度も「共に創る」を共有できて幸せでした。ありがとうございました。
新年度もよろしくお願いします(^^♪