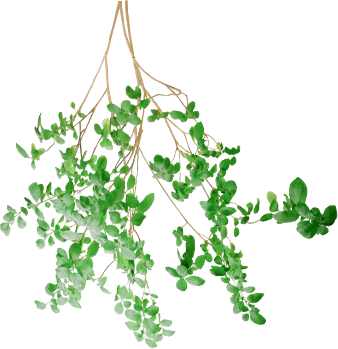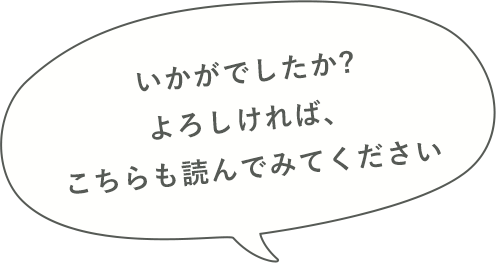「あめゆじゅとてちてけんじゃ」~賢治を読む~
今日のブログのこのタイトル、「あめゆじゅとてちてけんじゃ」が印象的な詩を、皆様ご存知でしょうか。
高校の国語の教科書にも掲載されている有名な作品なので、一度は聞いたことがある方が多いかと思います。
宮沢賢治の、「永訣の朝」です。
永訣の朝
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
(*あめゆじゆとてちてけんじや)
うすあかくいつそう陰惨な雲から
みぞれはびちよびちよふつてくる
(あめゆじゆとてちてけんじや)
青い蓴菜のもやうのついた
これらふたつのかけた陶椀に
おまへがたべるあめゆきをとらうとして
わたくしはまがつたてつぱうだまのやうに
このくらいみぞれのなかに飛びだした
(あめゆじゆとてちてけんじや)
蒼鉛いろの暗い雲から
みぞれはびちよびちよ沈んでくる
ああとし子
死ぬといふいまごろになつて
わたくしをいつしやうあかるくするために
こんなさつぱりした雪のひとわんを
おまへはわたくしにたのんだのだ
ありがたうわたくしのけなげないもうとよ
わたくしもまつすぐにすすんでいくから
(あめゆじゆとてちてけんじや)
はげしいはげしい熱やあへぎのあひだから
おまへはわたくしにたのんだのだ
銀河や太陽 気圏などとよばれたせかいの
そらからおちた雪のさいごのひとわんを……
……ふたきれのみかげせきざいに
みぞれはさびしくたまつてゐる
わたくしはそのうへにあぶなくたち
雪と水とのまつしろな二相系をたもち
すきとほるつめたい雫にみちた
このつややかな松のえだから
わたくしのやさしいいもうとの
さいごのたべものをもらつていかう
わたしたちがいつしよにそだつてきたあひだ
みなれたちやわんのこの藍のもやうにも
もうけふおまへはわかれてしまふ
(*Ora Orade Shitori egumo)
ほんたうにけふおまへはわかれてしまふ
あああのとざされた病室の
くらいびやうぶやかやのなかに
やさしくあをじろく燃えてゐる
わたくしのけなげないもうとよ
この雪はどこをえらばうにも
あんまりどこもまつしろなのだ
あんなおそろしいみだれたそらから
このうつくしい雪がきたのだ
(*うまれでくるたて
こんどはこたにわりやのごとばかりで
くるしまなあよにうまれてくる)
おまへがたべるこのふたわんのゆきに
わたくしはいまこころからいのる
どうかこれが天上のアイスクリームになつて
おまへとみんなとに聖い資糧をもたらすやうに
わたくしのすべてのさいはひをかけてねがふ
註
*あめゆきとつてきてください
*あたしはあたしでひとりいきます
*またひとにうまれてくるときは
こんなにじぶんのことばかりで
くるしまないやうにうまれてきます
宮沢賢治が愛する妹トシの死に際し書いたこの詩。
この詩について深く掘り下げていく前に、桜井先生の口から2つの衝撃の事実を知ったタナカ。
まず1つ、
この「永訣の朝」という作品やタイトルから、賢治はこの詩をトシの今際の際に書いたと思っている人が多いけれど、実はトシの臨終の際には賢治は押し入れに顔を入れ泣きじゃくっているだけだった。この詩は賢治が妹の死をあとから振り返って書いたものである。
2つめ、
賢治の妹トシが亡くなったのは彼女が24歳の時、賢治が26歳の時であった。
「え、これってほんまに❝永訣の朝❞に書いた『永訣の朝』じゃないんや!?」
「え、もっと小さな妹に対して送った詩かと思ってた!!賢治26歳やったんや!?トシ24歳って結構大人な妹に対してこの詩送ったんやな!?」
と、目から鱗が落ちたタナカ。
元々、この詩は幼い妹が死の淵に近づこうとしているまさにその時に賢治が書いたものだとばかり思い込んでいたのですが、たったこれだけの事実を知ることで、この詩の見え方が少し変わってきました。
そしてここから読解のスタート。
読んでいく中で「?」を感じたところをとりあげ、それに対する自分の意見を述べていきます。

「『みぞれはびちよびちよふってくる』と『みぞれはびちよびちよ沈んでくる』の違いって?」
―「ふってくる」はみぞれの落下を空を見上げて見ている感じ、「沈んでくる」は雪原にみぞれが落ち雪がにじむのを見ている、地面を見ている感じがする…視点の変化を感じるなぁ
「『これらふたつのかけた陶椀に』の陶椀はなぜふたつでなくてはいけないの?」
―「おまへ」と「みんな」とにもたらす「聖い資糧」だから「ふたつ」なのかな?でも「おまへがたべるあめゆきをとらうとして」いると書いてあるよなぁ…
「『まがつたてつぽうだまのやうに』ってどんな様子?」
―普通の「鉄砲玉のように」ではなく「まがったてっぽうだま」なわけだから、妹の死に動揺してまっすぐ歩けていないことを表現したいのかなぁ
「『わたくしもまつすぐにすすんでいくから』の『も』に込められた意味とは?」
―「わたくしをいつしやうあかるくするために/こんなさつぱりした雪のひとわんを/おまへはわたくしにたのんだのだ」とあるように、妹トシは他者への配慮を持ち生きていた人間で、今際の際にあっても賢治のために雪のひとわんを頼んだと賢治は受け取ったのだとしたら、「おまえのように他者に思いをかけ生きる」という意味で「わたくし『も』」なのかな?
「『Ora Orade Shitori egumo』がローマ字表記になっている意味って?」
―これまで志を同じくしてきた妹が発したこの言葉を受けとめきれておらず、賢治自身が言葉の意味を昇華しきれていないから…?

こんな疑問と意見(もちろんこれだけでなくほかにもたくさん)が皆から出てきました。
学びの森の桜井ゼミでの文学作品の読解の時間は、いつもこんな様子です。
桜井先生から提示される情報を補助線にしたりしなかったりしながら、各々本文を読み、自分の中に生まれた「?」を言葉にし、それに対する自分なりの答えを根拠と共に言語化する。
それが文学研究の見地から見て間違っているか否かはあまり関係がなく、本文に根拠があってそれを説明できれば、いくらでも自由に読んでいい。
こうした幅のある読みが許される環境で「読む」経験は、意外にも最終的には「本文に帰る」ことを促すものだなと思います。
本文に対する自分の読み、自分の意見を主張するには本文に根拠を探さなければならず、本文に根拠を探すには徹底的に本文にこだわり、本文をよく読むしかないからです。
本文をよく読む経験は情報を正確に読み解く力を、それをもとに自身の考えを構築する経験は論理的な思考力を、それを言語化し主張する経験は表現力を鍛えることにつながります。
桜井ゼミでは、この「永訣の朝」と「松の針」に「無声慟哭」、そして「青森挽歌」という、妹トシの死が影響を与えた賢治の詩を3~4週ほどかけて読み込んでいきました。
しかしどれだけ本文にこだわりよく読んでも、依然わからないことだらけなのが賢治の作品。
賢治自身が「心象のスケッチ」と語ったこれらの作品を我々がテキストを通して垣間見たところで、賢治の心象全てを読み取り、理解できることなどあり得ないのでしょう。(というか、もしそんなことが出来ちゃったら文学はなんとつまらなくなってしまうことでしょう。)
「なぜこう書いてあるの?」「わからない」と思うからこそ本文を繰り返し読み、なんとか自分の「読み」「意見」を持とうと根拠を探す。皆と意見を共有し、交換し、また考える。それでも「なぜ」「わからない」に打ちのめされる。それでも(だからこそ?)なぜか胸を掴むものが確かにあり、読んでいる「私」の心を揺さぶる。また「なぜ」と本文に戻る…。
思えば高校生の頃に授業で「永訣の朝」を読んだ時は、こんなにもやもや「わからない」とは思わなかったのです。「なんと美しい兄妹愛の詩だ」と感動し、すっきりさっぱり心の引き出しにしまっていました。
ところが今、読めば読むほどわからない賢治。
「…わからんな」「…そうですね」「…難しいですね」「でも、おもろいな」「そうですね」。
生徒とそんなやりとりをしながら、すっきりしない思いを抱えたまま、授業を終えました。
ひょっとしたら、このいつまでも残る「?」を共有し合えるこの感じ、誰かと共同で文学を読む醍醐味かもしれません。